「施工管理技士の試験を受けたいけど、実務経験の証明ってどうやるの?」
「自分の経歴が実務経験として認められるか不安…」
「もう辞めちゃった会社の経験って、証明してもらえるんだろうか…?」
施工管理技士を目指す多くの方が、この「実務経験証明書」という大きな壁にぶつかります。
制度が変わって受験しやすくなったと聞くけれど、結局のところ、二次検定には実務経験が必須。そして、その経験を”公式に”証明できなければ、スタートラインにすら立てないのが現実です。
ご安心ください。この記事では、そんなあなたの不安や疑問を解消するために、
- 令和6年度からの新制度で実務経験の扱いがどう変わったか
- 認められる工事・認められない業務の具体的なライン
- 【超重要】実務経験証明書の具体的な書き方(記入例つき)
- 退職した会社への依頼方法や、万が一のトラブル対処法
など、「実務経験の証明」に関するすべてを、どこよりも分かりやすく、徹底的に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたは自信を持って実務経験証明書を作成し、合格への第一歩を踏み出せるはずです。
そもそも施工管理技士に実務経験は必要?令和6年からの新制度をサクッと解説
「実務経験がなくても受験できるようになった」と聞いて、少し混乱している方もいるかもしれませんね。まずは制度の変更点を正しく理解しておきましょう。
結論から言うと、一次検定と二次検定で扱いが全く異なります。
第一次検定
令和6年度から、学歴や実務経験に関係なく、1級は19歳以上、2級は17歳以上であれば誰でも受験可能になりました。これに合格すれば、晴れて「技士補」の資格が得られます。これは大きな変更点で、学生や未経験者でも挑戦の門戸が大きく開かれました。
第二次検定
ここが重要です。技士補ではなく、正式な「施工管理技士」になるために必須の第二次検定では、これまで通り、規定の実務経験が必須です。
つまり、「技士補」には実務経験なしでなれるけど、「施工管理技士」になるには、必ず実務経験とその証明が必要、ということです。だからこそ、この「実務経験証明書」の作成が避けて通れない道なのです。
あなたの経験は大丈夫?実務経験として「認められる工事」と「認められない工事」
「自分のやってきた仕事って、実務経験になるのかな?」これは誰もが不安に思うポイントです。証明書を書く前に、自分の経歴が実務経験としてカウントできるかを確認しましょう。

認められる実務経験の例
基本的には、建設工事の施工に直接関わる技術的な経験が対象です。具体的には、施工管理(工程、品質、安全、原価)、施工計画の作成、測量、積算、設計変更に伴う図面作成などが該当します。
【建築施工管理の場合の工事例】
- 建築一式工事: 事務所ビル建築工事、共同住宅新築工事、学校増築工事、店舗改修工事など
- 躯体工事: 杭工事、鉄骨建方工事、型枠工事、コンクリート打設工事など
- 仕上げ工事: 内装仕上げ工事、外壁塗装工事、防水工事、屋根葺き替え工事など
- 解体工事: 建築物解体工事
【特に注意!】実務経験として認められない業務
どんなに長く建設業界にいても、以下の業務は実務経験として認められません。もし、これらの業務経験しか証明できない場合、受験資格を満たさない可能性が高いので注意してください。
- 施工に直接関わらない業務
- 設計事務所等での設計のみの業務(施工管理者が行う設計変更などは除く)
- 積算事務所での積算のみの業務
- 不動産会社での用地買収や管理業務
- CADオペレーターとしての作図業務のみ
- 管理・維持業務
- 完成した建物の保守、点検、メンテナンス、維持管理
- ビルメンテナンス業務
- その他
- 営業、総務、経理などの事務作業
- 資材の搬入・運搬のみの作業
- コンサルタント業務
自分の経歴がグレーゾーンで判断に迷う場合は、必ず試験の実施機関である「一般財団法人 建設業振興基金」に問い合わせて確認しましょう。
【最重要】施工管理技士の実務経験証明書の書き方パーフェクトガイド
さて、いよいよ本題です。実務経験証明書の書き方を、ステップバイステップで、記入例を交えながら解説していきます。
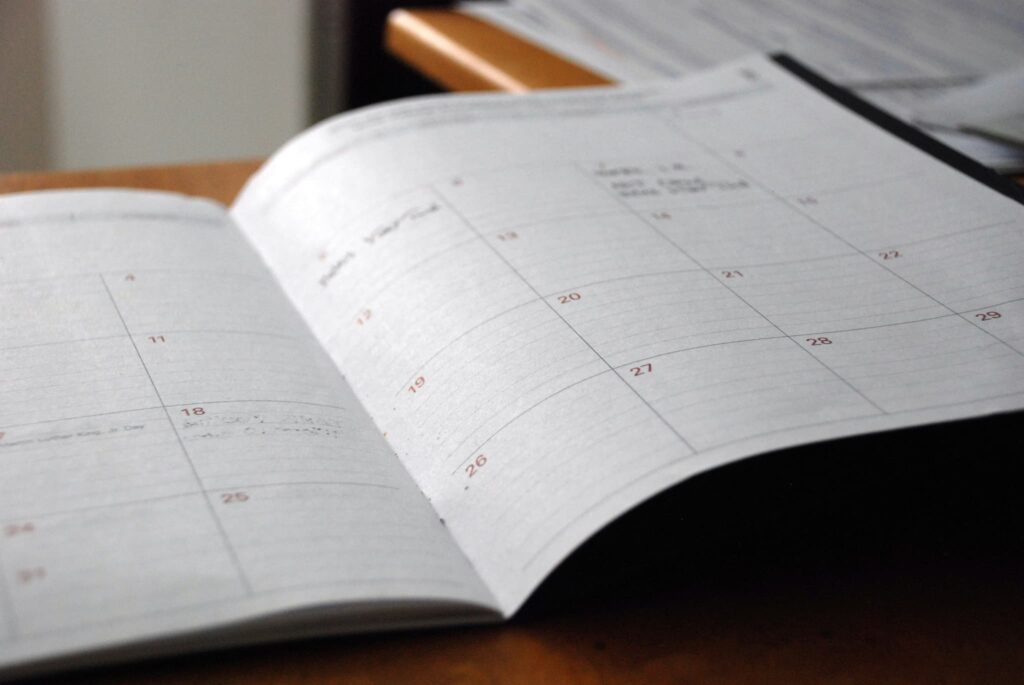
STEP1: まずは「実務経験証明書」の用紙を入手しよう
証明書の用紙は、受験申込書に同封されていますが、事前に準備したい場合は建設業振興基金のウェブサイトからダウンロードできます。必ず、受験する年度の最新の様式を使用してください。
STEP2: 【記入例つき】各項目の書き方を徹底解説
証明書で最も重要なのが「工事経歴」の欄です。審査員はここを見て、あなたの経験が受験資格を満たしているかを判断します。
【実務経験証明書 記入例(建築一式工事の場合)】
| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 発注者名 | 請負金額(千円) | 工事種別 | あなたの立場 | 具体的な工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○ビル新築工事 | 東京都千代田区○-○-○ | R2.4.1~R4.3.31 | △△株式会社 | 500,000 | 建築一式 | 現場代理人 | RC造地上10階建事務所ビルの新築工事において、現場代理人として施工計画の作成、工程管理(全体工程表、月間工程表の作成・調整)、品質管理(配筋検査、コンクリート受入検査の立会い)、安全管理(安全巡視、KY活動の指導)など、施工管理全般に従事した。 |
| □□マンション大規模修繕工事 | 神奈川県横浜市○区○-○ | R4.5.1~R5.2.28 | ××管理組合 | 80,000 | 建築一式 | 主任技術者 | SRC造15階建分譲マンションの大規模修繕工事において、主任技術者として居住者対応、外壁補修工事の品質管理(ひび割れ調査、打検)、仮設足場の安全管理、防水改修工事の工程管理を担当した。 |
書き方のポイント
- 工事名: 契約書に記載されている正式名称を正確に記入します。「○○邸新築工事」のように具体的に書きましょう。
- 工期: 自分がその工事に従事した期間を記入します。工事全体の工期ではないので注意してください。
- あなたの立場: 「現場代理人」「主任技術者」「監理技術者」「担当技術者」など、工事における正式な役職を書きます。単に「現場監督」や「作業員」と書くのは避けましょう。
- 具体的な工事内容: ここが最も重要です!審査員にあなたの経験が伝わるよう、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して具体的に書きます。
- 建物の構造(RC造、S造など)、規模(地上○階建、延床面積など)を入れる。
- 自分が担当した管理業務(工程・品質・安全など)を具体的に記述する。
- 「~の管理を行った」「~に従事した」など、能動的な表現で書く。
STEP3: 会社に証明印をもらう際のポイント
記入が完了したら、会社に証明印(社印および代表者印)をもらいます。スムーズに進めるためのコツは以下の通りです。
- 誰に頼むか: 原則として本社の代表取締役です。支店採用などの場合は、権限を委譲された支店長でも可能な場合があります。事前に総務や人事に確認しましょう。
- 依頼のタイミング: 締切ギリギリは絶対にNG。担当者も忙しいので、最低でも提出期限の2~3週間前には依頼するのがマナーです。
- 準備しておくこと:
- 必要事項をすべて記入し、捺印箇所を付箋などで分かりやすく示した「実務経験証明書」
- 依頼内容を簡潔にまとめた添え状
- (郵送で依頼する場合)切手を貼った返信用封筒
丁寧な準備と早めの行動が、円滑な証明書取得の鍵です。
よくあるお悩み別!実務経験証明のQ&A
ここからは、多くの方が悩むであろうケースについて、Q&A形式で解説します。
Q1. 既に退職した会社の実務経験を証明したい場合は?
A. 原則、その退職した会社に依頼する必要があります。
企業には実務経験を証明する義務はありませんが、協力してくれるケースがほとんどです。
- 連絡方法: まずは電話で人事部や総務部に問い合わせ、担当者と必要書類を確認します。突然書類を送りつけるのはマナー違反です。
- 郵送依頼: 郵送で依頼するのが一般的です。その際は、上記「STEP3」で解説した準備物に加え、丁寧な依頼状を同封しましょう。なぜ証明書が必要なのか(資格取得のため)を誠実に伝えます。
- 万が一、協力を拒否されたら: 残念ながら、法的な強制力はありません。しかし、まずは「なぜ協力いただけないのか」を冷静に確認しましょう。どうしてもダメな場合は、試験実施機関である建設業振興基金に事情を説明し、対処法がないか相談してみてください。
Q2. 会社が倒産・廃業してしまったら…?
A. 諦めないで!まずは試験実施機関に相談してください。
会社の代表者がいなくても、破産管財人などが証明してくれるケースがあります。また、元上司や同僚による第三者証明(別途、所定の手続きが必要)が認められる可能性もゼロではありません。このような特殊なケースは、独断で諦めず、必ず建設業振興基金に直接問い合わせて指示を仰いでください。
Q3. 派遣社員や出向の場合、証明者は誰になる?
A. 雇用契約によって異なりますが、一般的には「派遣元」の会社です。
あなたの給与を支払っている雇用主(派遣元)が証明者となるのが基本です。
ただし、実際の業務内容は派遣先でしか把握できないため、派遣先の上長に工事内容を証明してもらい、それをもとに派遣元の代表者印をもらう、といった手続きが必要になることがあります。
この場合も、早めに派遣元・派遣先の両方に相談しましょう。
Q4. 証明内容に虚偽記載をしたらどうなる?
A. 絶対にやってはいけません。バレたら人生を棒に振る可能性があります。
実務経験が少し足りないからといって、工期を延ばしたり、関わっていない工事を書いたりする虚偽記載は「不正行為」です。発覚した場合、
- その試験は無効、合格は取り消し
- 一定期間(最大3年間)の受験資格停止
- 建設業法違反として、会社にも行政処分が下る可能性
など、非常に重いペナルティが科せられます。
リスクがあまりにも大きすぎます。必ず、事実に基づいた正確な内容を記載してください。
【新旧どっちがお得?】二次検定の受験資格と最短合格ルート
令和6年からの新制度と、令和10年度まで経過措置として残されている旧制度。二次検定を受けるにあたり、自分はどちらが有利なのか気になりますよね。
- 旧受検資格: 学歴によって必要な実務経験年数が決まる。(例:大卒指定学科なら3年以上)
- 新受検資格: 学歴は不問。一次検定合格後の実務経験年数で決まる。(例:1級一次合格後、特定実務経験1年を含み3年以上など)
どちらのルートを選ぶべきか?
- 学歴が高く、既に長い実務経験がある方: 経過措置期間中に旧受検資格で受験した方が、必要な実務経験年数が短くなる可能性があります。
- 学歴に自信がない、または実務経験が浅い若手の方: まずは新制度で一次検定に合格(技士補になる)し、そこから必要な実務経験を積んでいくのが王道ルートです。
特に、1級技士補の資格があれば「監理技術者補佐」として大規模な工事に関わるチャンスが増え、結果的に質の高い実務経験(特定実務経験など)を積みやすくなるという大きなメリットがあります。
自分の学歴と現在の実務経験年数を照らし合わせ、建設業振興基金のウェブサイトで両方の受験資格をよく確認し、最適なルートを選択しましょう。
【失敗しない転職】あなたに合ったサービスは?目的別おすすめ3社を徹底比較

「転職したいけど、どのサービスを使えばいいかわからない…」
転職活動は、いわば情報戦です。一人で戦うよりも、強力な武器を持つことで、成功率は劇的に上がります。その最強の武器が、「求人サイト」と「転職エージェント」の2つです。
それぞれの長所を理解し、両方に登録して「使い分ける」ことが、理想の会社と出会うための最短ルートです。ここでは、代表的な3つのサービスを比較し、あなたに最適な組み合わせを見つけましょう。
| リクルートエージェント | リクナビNEXT | パソナキャリア |
|---|---|---|
| サービス種別 転職エージェント | サービス種別 求人サイト | サービス種別 転職エージェント |
| 特徴 業界No.1の圧倒的な求人数 一般には出回らない非公開求人が豊富 全業界・全職種をカバー | 特徴 国内最大級の求人サイト 自分のペースで求人を探して応募できる 自己分析ツールが充実 | 特徴 ハイクラス・管理職の求人に強い 丁寧で親身なサポートに定評あり 女性の転職支援にも厚い実績 |
| こんな人におすすめ 多くの求人から選びたい キャリアの選択肢を広げたい まずはここに登録が必須 | こんな人におすすめ どんな求人があるか市場感を知りたい 自分のペースで活動を進めたい スカウト機能も使いたい | こんな人におすすめ 年収アップを目指す30代以上 専門的なキャリア相談をしたい 手厚いサポートを受けたい |
| 公式サイトで 無料キャリア相談 | 公式サイトで 求人をチェック | 公式サイトで 無料キャリア相談 |
【結論】最強の戦略は、まず「リクナビNEXT」で市場感を掴みつつ、業界最大手の「リクルートエージェント」と、ハイクラス・丁寧なサポートに定評のある「パソナキャリア」の両方に登録し、紹介される求人を比較検討することです。全て無料なので、3つ登録してもリスクはありません。
まとめ:正確な実務経験証明が、合格への最短切符
今回は、施工管理技士の「実務経験証明」について、これでもかというほど詳しく解説しました。
最後に、最も重要なポイントを繰り返します。
- 二次検定には実務経験とその証明が絶対に必要。
- 証明書の工事内容は具体的に、事実に即して書くこと。
- 虚偽記載は絶対にNG!
- 退職や倒産など、困ったことがあれば一人で悩まず試験実施機関に相談すること。
実務経験証明書の作成は、正直なところ面倒な作業です。しかし、これはあなたのこれまでのキャリアを公式に証明し、次のステップに進むための大切な儀式です。
この記事を参考に、自信を持って書類を準備し、施工管理技士合格という大きな目標を掴み取ってください。あなたの挑戦を心から応援しています!



